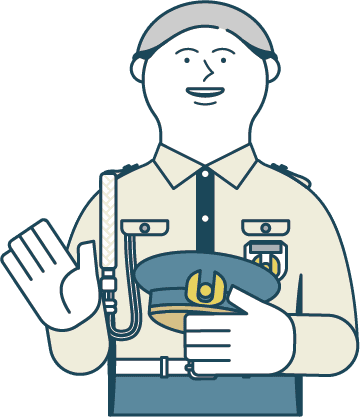警備について
ABOUT SECURITY
当社が行っている『警備業務』は、『警備業法』によって定められた業務です。
警備業法によって『認定』を受け、行う業務や地域、服装などを届け出て、
採用時の確認や教育・指導監督、検定資格者の配置基準などを遵守して行っています。
なお、警備対象は、契約したお客様又はその所有(使用)権の及ぶ範囲が基本となります。
それ以外の対象は対象者、対象物の所有(使用)権を持つ者の同意を確認した後に請負を判断させて頂きます。
当社が行っている『警備業務』は、『警備業法』によって定められた業務です。警備業法によって『認定』を受け、行う業務や地域、服装などを届け出て、採用時の確認や教育・指導監督、検定資格者の配置基準などを遵守して行っています。
なお、警備対象は、契約したお客様又はその所有(使用)権の及ぶ範囲が基本となります。それ以外の対象は対象者、対象物の所有(使用)権を持つ者の同意を確認した後に請負を判断させて頂きます。
施設警備(一号業務)

施設警備(一号業務)
警備業法第二条第1項第一号に定められた『事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務』です。
そのうち機械警備業務は比較的新しい形態となるため、第二条第5項にて一号業務の一種として定義されています。
常駐警備
『人』やそれを補助する『機器』を使用して施設等で行う施設警備です。『人』による柔軟さと『機器』による正確さを合わせることにより、お客様の業務に一番密着した警備です。
機械警備
各所に感知用の『警備業務用機械装置』を設置して当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器にて常時監視し、異常があった場合には警備員が急行して対処する警備です。(当該施設内のみで行う機器による警備は『ローカルシステム』と言います。)
特別に『五項業務』と言われる場合もあります。
監視業務
特定の物や場所に対して『人』や『機器』を使用して監視を行う施設警備です。高価な物や大切な物、会場設営後等の一時的な展示や設置した物に対してご用命ください。
巡回警備
施設内外の警備員が徒歩や車両にて点検を行う警備です。
時間としては定時と不定時、巡回ルートとしては定線と乱戦を組み合わせて警備員の姿を見せ、防犯や異常の早期発見に努めます。
交通誘導雑踏警備(二号業務)

交通誘導 雑踏警備(二号業務)
警備業法第二条第1項第一号に定められた『人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務』と定義された業務です。
交通誘導警備業務
主に道路(車道や歩道、その他一般交通の用に供する場所)にて行われる誘導業務。
福岡県公安委員会が指定した特定の路線(歩道なども含みます。また、路線外であっても特定路線に影響が及ぶ場合も含みます。)には、交通誘導警備業務の検定資格者の配置が必要となります。
また、食事休憩が交代制の現場では基本的に2級検定者を余分に配置する必要があります。
雑踏警備
イベントや祭礼、撮影の現場など人が雑踏する場所で雑踏事故を防止するために行う警備業務です。
人を並べたり、人の入場制限をかける場合は、規模の大小に関わらず全て雑踏警備業務となります。雑踏警備業務の検定資格者の配置が必要となります。
貴重品運搬警備(三号業務)

貴重品運搬警備(三号業務)
警備業法第二条第1項第三号に定められた『運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務』です。
現金を輸送する『現金輸送警備業務』が有名ですが、有価証券や貴金属、美術品の運搬もこの業務です。
『運搬』が業務であるため、『貨物自動車運送事業法』も遵守しています。
身辺警備(四号業務)

身辺警備(四号業務)
警備業法第二条第1項第四号に定められた『人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務』です。
警備対象が『人』となりますので、対象者の動向や移動、周辺状況を把握し、綿密な打ち合わせが必要なため、実施までに相当な期間を要します。